はじめに
今回の記事は、私がこれまでの勉強やクライアント様との施術・セッションを通して得た経験をもとにまとめています。
あくまで私自身の経験や学びをもとにした考察として、参考程度に読んでいただければ幸いです。
試合中や練習中に痛みが出たり、シーズンが終わる頃に体のあちこちが痛くなるという経験をしたことはありませんか?
その痛みの原因の多くは「筋肉の機能低下」によるものと考えます。
つまり、筋肉が正しく使えていない状態です。
痛みの原因は大きく2パターン
① シンプルに怪我をした場合
肉離れや捻挫、転倒など。明確な負傷なので、トレーニングでの改善は難しく、施術が必要になります。
② 機能低下による痛み
筋力の低下や使えていない筋肉が原因で、体が本来の動きをできなくなっているケース。
この場合は、トレーニングを通じて筋肉の機能を取り戻すことで、痛みの軽減や動きの改善が期待できます。
怪我は「治す」よりも「予防できる」
発生してしまった怪我をトレーニングで治すことは難しいですが、予防することは十分に可能だと考えています。
たとえば、
ギックリ腰は、腹直筋や腹横筋などの体幹(インナーマッスル)を鍛えることで予防できる。
肉離れは、負荷に耐えられる筋力と筋持久力を高めることで再発を防げる。
また、レントゲンで骨に異常が見られないのに痛みがある場合、その一因として「筋肉が現状の負荷に対応しきれていない」状態が考えられます。
このようなケースでは、1〜2週間の休養で痛みが引くことがほとんどですが、限界を超えて無理を続けてしまうと、肉離れや疲労骨折など、長期離脱につながってしまいます。
テーマに戻りましょう
私がこのテーマで一番大切だと感じているのは、
「練習による負荷に耐えられる身体をつくること」です。
ここで言う“トレーニング”とは、いわゆる筋肉を大きくするためのものではありません。
むしろ、今ある筋肉をどれだけ正しく使えるようにするか(=筋肉の促通を高めるか)がポイントです。
筋トレは“筋肉を増やす”だけでなく、“筋肉を使えるようにする”ためのリハビリでもあります。
この「使える筋肉」をつくることこそが、怪我の予防に直結するトレーニングの本質だと私は考えています。
現役・引退後に関わらず、同じことが言える
例えばこんな経験はありませんか?
昔は1日中ボールを投げても翌日それほど筋肉痛にならなかったのに、
引退してから久しぶりにキャッチボールや試合に出ると、翌日以降に強い筋肉痛が出た——。
しかも不思議なことに、その日は意外とプレーできるんですよね。
でも、数日〜1週間ほどで痛みは引きます。
ところが、また同じような運動をすると再び痛みが出てしまう……。
この現象にはしっかりとした理由があると考えます。
現役時代は毎日のようにボールを投げ、走り、トレーニングをしていたため、
その負荷は当時の体にとって“日常的で問題のないレベル”でした。
しかし、引退後はどうしても運動の頻度や強度が低下します。
その結果、体は徐々に「その負荷に耐える準備」をしなくなり、筋肉の働き(機能)が低下してしまうのです。
このときの痛みは「怪我」ではなく、筋肉の機能低下による一時的な反応です。
しばらく安静にすれば自然と和らぎますが、筋肉の使い方が戻っていない限り、再び同じ負荷をかけると、また同じ痛みを繰り返してしまいます。
私の経験的に、このような機能低下の場合は、施術によって症状が和らぐケースも多くあります。
ただ、筋力(筋機能)は施術だけでは回復しないことが多いため、痛みの程度が減った段階で少しずつ動きを取り戻していくことが重要です。
見方を変えれば、痛みの程度が減れば、ボールを投げることのできる数が増えるので、機能回復を促進することも可能だと考えます。
現役選手にも同じことが言えます
今までは引退後のケースを中心に話してきましたが、現役の選手にも全く同じことが言えます。
現役選手で大切になってくるのは、「どれだけの量をこなせるか」。
経験的に、量をこなす体力のある選手はやっぱり強いなと感じます。
※施術でも同じで、体力のある先生ほど多くの症例に関わる機会が増え、経験の幅が広がると感じます。
これは“無意味にたくさんやれ”という話ではなく、
「質を落とさずに、どれだけ量をこなせるか」という意味です。
たとえば、50回のフルスイングでバテる選手と、100回フルスイングできる選手を比べると、
やはり100回できる選手の方が強く、さらに50回分の経験も積めます。
「このスイングはしんどい」「このフォームなら無駄な力が抜ける」など、量をこなす中でしか気づけないことがあります。
このように、量をこなせる体をつくることが、結果的にケガの予防や体力向上につながります。
重要なのは、無理に数をこなすのではなく、自分の体に合ったトレーニングを段階的に行うこと。
目的を持って量を積み上げることで、最終的に質の高いパフォーマンスが生まれます。
効果的なトレーニング方法とは?
では、実際にどんなトレーニングが効果的なのでしょうか?
結論から言うと、しっかりとした刺激量を確保できるトレーニングを行うことが大切です。
特におすすめなのが、いわゆるBIG3と呼ばれる基本種目です。
- スクワット
- デッドリフト
- ベンチプレス
これらは全身の大筋群をバランスよく使うため、筋肉への刺激量が非常に大きく、機能回復に効果的です。
目安としては、最大負荷の80%程度で行うのがおすすめ。
トレーニング後に筋肉痛が3〜4日ほどでおさまる程度の負荷が、目安として適しています。
補助的な種目としては、チンニング(懸垂)やブルガリアンスクワットなども効果的です。
ジムに行けない方でもできる自宅トレーニング
もしジムに通うのが難しい場合でも大丈夫。
自宅でも十分に効果を出すことができます。
- 腕立て伏せ
- スクワット
- ブルガリアンスクワット
- クランチやプランク
これらの基本的な自重トレーニングを行い、さらにトレーニングチューブを使うことで負荷をコントロールすれば、より効率的に筋肉へ刺激を与えることができます。
継続こそ最大のポイント
そして最も大切なのは、「継続」です。
一度に大きな負荷をかけるよりも、1日30分程度のトレーニングを週3回ほど、無理なく続けることがポイント。
この「適度な刺激」と「継続的なトレーニング」によって、筋肉の機能が高まり、結果として怪我の予防とパフォーマンスの向上につながります。
まとめ
筋トレは、「パワーをつける」「強いボールが投げられる・蹴れる」「速く走る」「高く飛べる」「体を大きくする」などのイメージが強いですが、
これらの結果の前に、まずは「ケガを防ぐ」という重要な役割があります。
特にこれからは、春に向けてシーズンオフになります(ウィンタースポーツは今からがシーズンですが)。
春から進学する選手、最後のシーズンを迎える選手など目的はそれぞれ違うと思いますが、
ケガで悩まなくて良いように、今のうちにやれることをしっかりやり切りましょう!
ご質問などありましたら、お問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。
トレーニングに関するお悩みやメニュー作成のヒントなども、できる限りお答えいたします。
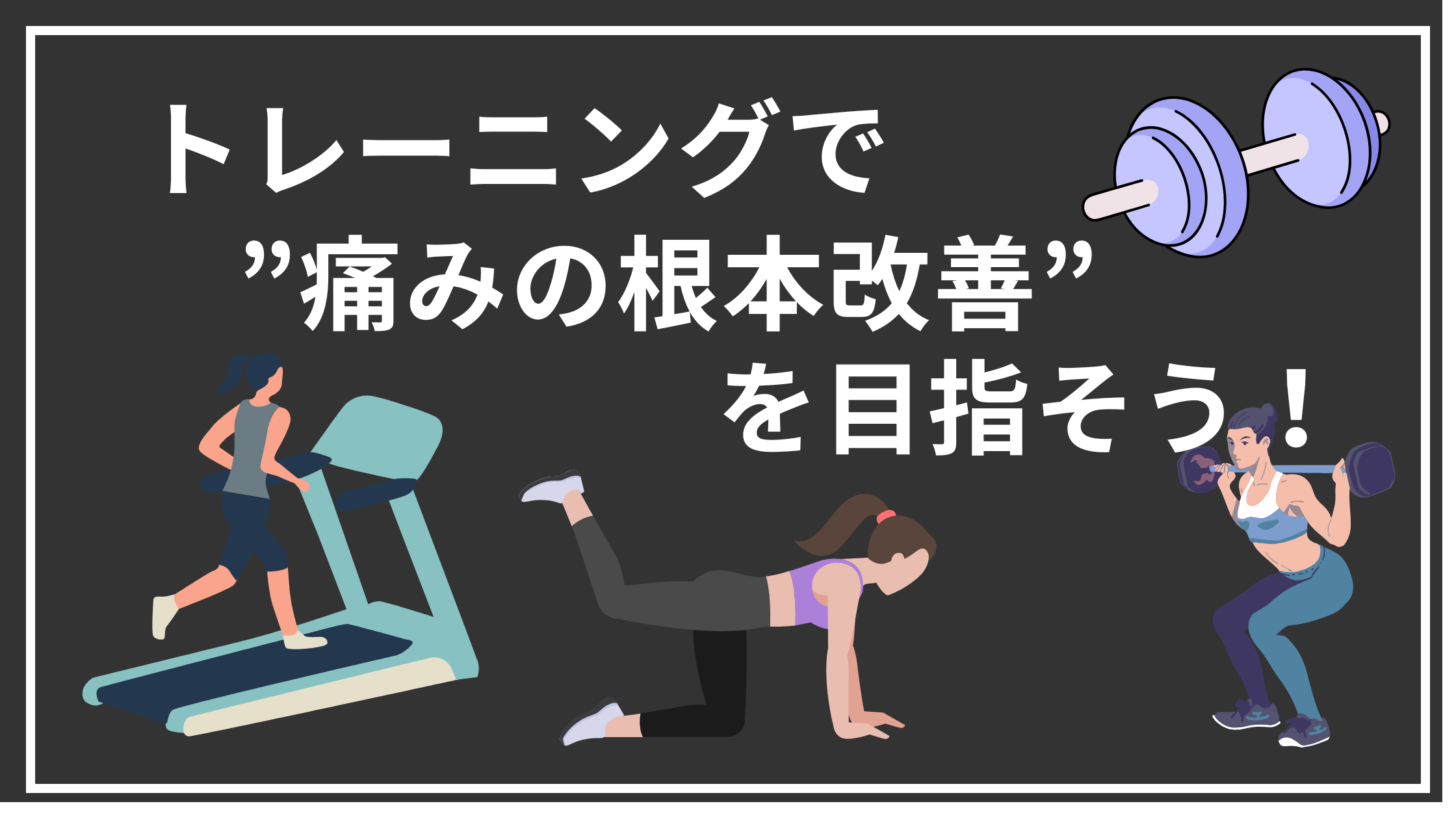
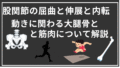
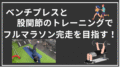
コメント